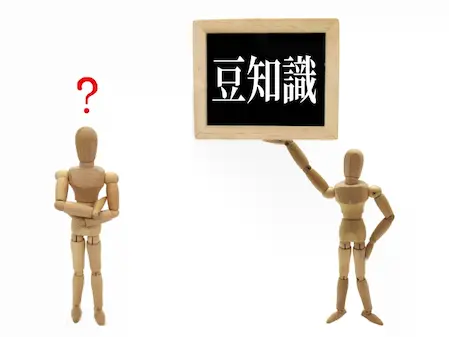企業経営において資金繰りの悪化は避けて通れない課題です。
売上の減少や取引先の倒産、景気変動などにより、借入金の返済が一時的に困難になることも少なくありません。こうした状況で活用されるのが「リスケジュール(Reschedule)」です。
本記事では、リスケジュールの基本的な意味から制度的背景、実務上の注意点までを、専門家の視点からわかりやすく解説します。
リスケジュールの定義と基本的な考え方
リスケジュールとは、金融機関などの債権者と債務者が合意のうえで、既存の借入契約における返済条件を見直すことを指します。
具体的には、返済期間の延長、返済額の減額、一時的な元金返済の猶予(元金据置)などが行われます。つまり、債務不履行を防ぐための「条件変更交渉」です。企業再建や経営改善の初期段階で用いられることが多く、債務整理や倒産手続きに入る前の“延命策”とも言える手段です。
リスケジュールの制度的背景と金融行政の位置づけ
リスケジュールは、2008年のリーマンショック後から徐々に認められやすくなりました。
金融庁は「中小企業金融円滑化法」(2009年施行)により、金融機関に対して中小企業の資金繰り支援を求める方針を打ち出しました。この法律自体は2013年に終了しましたが、その後も金融庁の監督方針として「金融仲介機能の発揮」や「事業再生支援の重視」が続いており、リスケジュールは実務上、今も重要な経営改善ツールとして位置づけられています。
銀行側にも「貸倒れを防ぐ」というメリットがあるため、制度的にも柔軟な対応が促されています。
リスケジュールの具体的な手続きと流れ
リスケジュールを行う場合、まずは債務者が金融機関に対して「返済条件の変更申出書」や「資金繰り計画書」を提出します。この際、経営改善計画の実現可能性が重視され、単なる支払い延期ではなく「返済再開の見通し」が求められます。
行政書士や中小企業診断士などの専門家が計画書の策定を支援するケースも多く、信頼性を高めるうえで重要な役割を果たします。交渉がまとまれば、変更契約書を締結し、新たな返済スケジュールが開始されます。
リスケジュールと新規融資の関係
注意すべきは、リスケジュールを行った場合、新規の融資が受けられないことです。金融機関から見れば格付けを下げざる負えないため、経営者にとっては大きな判断材料となります。
ただし、誠実な経営改善の姿勢を示し、実行計画を確実に遂行していけば、信用回復は十分に可能です。専門家の助言を得ながら、業績の回復と信頼関係の維持を意識することが肝要です。
リスケジュールと他の再生手法との違い
リスケジュールは、民事再生や私的整理のような「債務削減」を伴う手続きではなく、あくまで返済条件の調整にとどまる点が特徴です。そのため、法的手続きよりも柔軟でスピーディーに進められる一方、根本的な財務改善には至らない場合もあります。
経営改善の一環として、コスト削減や収益構造の見直しと併せて実施することが不可欠です。
リスケジュールを検討する際の注意点と専門家の関与
リスケジュールは「時間を稼ぐ」だけの対策ではなく、経営再建の第一歩です。
金融機関との交渉では、誠実な説明と情報提供が不可欠であり、いい加減な数字や根拠のない計画では合意に至りません。
行政書士などの専門家に早期相談し、資金繰りの見通しや再生計画の妥当性を客観的に検証してもらうことが重要です。特に複数の金融機関と取引がある場合、交渉の整合性を保つためにも専門家の調整力が大きな価値を発揮します。
まとめ
リスケジュールは、経営危機を乗り越えるための有効な手段であり、金融機関との信頼関係を再構築する契機にもなります。ただし、その実効性は、経営者の真摯な姿勢と実現可能な改善計画にかかっています。
単なる返済延期ではなく、再生のための戦略的な手段として位置づけ、専門家の支援を受けながら計画的に進めることが、持続的な企業再生への近道となるでしょう。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】