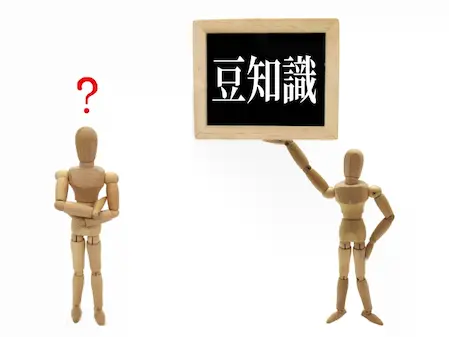創業時に金融機関から融資を受ける際、多くの経営者が気にするのが「返済開始のタイミング」です。
事業は立ち上げ当初ほど売上が安定せず、資金繰りに不安を抱えることが少なくありません。
そこで活用されるのが「返済据置期間」という仕組みです。
これは創業者が資金を有効に活用し、事業基盤を整えるための重要な制度といえます。本記事では、返済据置期間の仕組みやメリット、注意点について専門家の視点から解説します。
返済据置期間の定義と概要
返済据置期間とは、融資を受けた後、元金の返済を一定期間猶予してもらえる仕組みを指します。
この間は利息のみを支払い、元金返済は据え置かれるため、資金繰りの余裕を確保しやすくなります。
特に創業期の企業は売上が立ち上がるまで時間がかかるため、据置期間があることで事業資金を事業拡大や運転資金に回すことができます。日本政策金融公庫などの公的金融機関でよく導入されている制度です。
創業融資における返済据置期間の役割
創業期は仕入れや設備投資、人件費などの支出が先行する一方、売上は徐々にしか増えません。
そのため資金繰りが逼迫しやすいのが現実です。返済据置期間を設けることで、初期の半年から1年にわたり元金返済が不要となり、資金ショートのリスクを軽減できます。
例えば、日本政策金融公庫では最長で1年程度の据置が認められる場合があり、創業者にとっては大きな安心材料となります。
返済据置期間のメリットとデメリット
メリットは何といっても資金繰りの余裕を確保できる点です。
返済に追われず、事業に集中できるため、成長の加速につながります。
しかし一方で、据置期間が終われば据置期間分の元金が上乗せで返済が始まるため、毎月の返済額が少し大きくなる可能性があります。
士業から見た返済据置期間の活用ポイント
行政書士の立場からすると、返済据置期間の利用は創業計画書や資金繰り表の作成において重要な要素です。特に日本政策金融公庫の融資では、事業計画に基づき適切な据置期間を設定することが審査のポイントになります。専門家に相談すれば、資金繰りを長期的に見据えた計画づくりや、融資担当者への説明をスムーズに行うサポートを受けることができます。
返済据置期間を利用する際の注意点
据置期間を設けると、安心感から資金管理が甘くなるケースがあります。
しかし据置が終わった後には確実に元金返済が始まるため、その時期に売上や利益が追いついていなければ資金難に陥るリスクがあります。したがって、据置期間中に資金を投資して売上を伸ばす努力が必要です。また、融資条件によっては据置の長さに制限があるため、金融機関との綿密な打ち合わせが欠かせません。
まとめ
返済据置期間は、創業融資を受ける際に資金繰りの不安を和らげる有効な制度です。
しかし、猶予期間があるからといって油断は禁物で、据置終了後の返済開始を見据えた計画的な資金管理が不可欠です。
融資の申込み段階で返済据置期間をどう設定するかは、創業者にとって大きな経営判断となります。
活用を検討する際には、行政書士といった専門家に相談し、事業計画と資金繰りを万全に整えることを強くおすすめします。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】