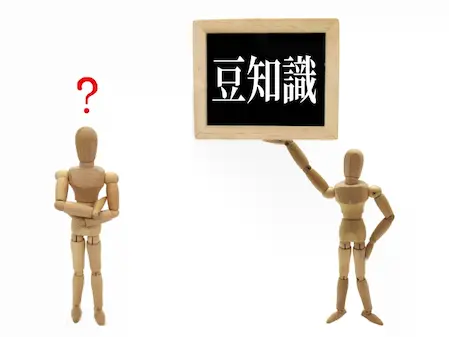企業経営において「決算書」は欠かせない存在です。
銀行融資や投資判断、さらには経営分析など、あらゆる場面で活用される財務情報の基礎資料といえます。特に融資審査の場では、金融機関が企業の経営状態を判断する最重要書類として提出が求められます。
本記事では、決算書の基本構成や読み解き方、そして融資審査での活用ポイントを、士業(税理士・行政書士など)の視点も交えて解説します。
決算書の定義と目的
決算書とは、企業が一定期間の経営成績と財務状況を明らかにするために作成する財務報告書の総称です。
主に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」の3つで構成され、これらを合わせて「財務三表」と呼びます。
企業は通常、1年間の会計期間終了後に決算を行い、税務申告や経営分析の基礎資料として利用します。
士業の立場から見ると、決算書は単なる数字の羅列ではなく、経営者が企業の健全性や将来性を外部に示すための「経営報告書」と位置づけられます。
貸借対照表が示す企業の財務状態
貸借対照表(B/S)は、決算日時点での企業の「資産」「負債」「純資産」を一覧化したものです。
これにより、企業がどれだけの資産を持ち、どのような資金で運用しているかを把握できます。
例えば、資産の中でも現金や売掛金が多ければ流動性が高く、短期的な支払い能力が強いと判断されます。一方で、負債が過大な場合は財務リスクが高まります。
金融機関はこの貸借対照表を通じて「返済能力」や「資金繰りの安定性」を見極めます。税理士や行政書士は、これらの数字を基に財務バランスを分析し、融資や改善策を提案する役割を担います。
損益計算書で見る収益力と経営効率
損益計算書(P/L)は、一定期間における企業の収益と費用を示し、その結果として「利益」がどれほど残ったかを明らかにします。
売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益などの段階的な利益を見ることで、企業の収益構造を理解することができます。
融資審査では、安定した営業利益を確保しているかが重要な評価ポイントです。
士業としては、過去数年の損益推移を比較し、収益力の持続性や経費構造の適正性を分析することが求められます。特に中小企業の場合、税務上の節税対策が利益に影響するため、税理士の助言が大きな意味を持ちます。
キャッシュ・フロー計算書が示す資金の流れ
キャッシュ・フロー計算書(C/F)は、企業の現金の流れを「営業活動」「投資活動」「財務活動」に区分して示す書類です。
黒字経営でも資金繰りが厳しい企業は少なくありません。
その原因を把握するために、この書類は欠かせません。たとえば営業キャッシュ・フローが安定してプラスであれば、本業でしっかり現金を稼げていると判断されます。
ただし、この書類を作成している中小企業は少ないのが現実です。
金融機関は、キャッシュフロー計算書よりも資金繰り表を用いて、返済原資が確保できるかを見極めます。行政書士や税理士は、資金繰り表を用いることで、融資や経営改善をサポートします。
融資審査における決算書の重要性
銀行などの金融機関が融資を検討する際、最も重視するのが決算書です。
過去3期分(公庫は2期分)の決算書を求められるのが一般的で、売上や利益の推移、負債の増減、自己資本比率などが詳細に分析されます。また、単に利益が出ているだけでなく、安定的な経営が継続できるかどうかが評価のカギとなります。
士業の立場では、融資を受けやすくするために「財務内容の見直し」や「事業計画書の作成支援」を行い、信頼性の高い資料作成をサポートします。
まとめ:決算書を正しく理解し、経営の武器にする
決算書は、単なる会計処理の結果ではなく、企業の「健康診断書」ともいえる重要書類です。
融資審査だけでなく、経営戦略や税務対策の判断にも欠かせません。中小企業経営者にとっては、決算書の数字を読み解き、自社の強みと課題を把握することが事業成長の第一歩となります。
もし内容の理解や作成に不安がある場合は、税理士や行政書士といった専門家に相談することで、より信頼性の高い財務資料を整え、金融機関や投資家に対して自信をもって説明できる体制を整えることが重要です。
詳細はこちら|融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】