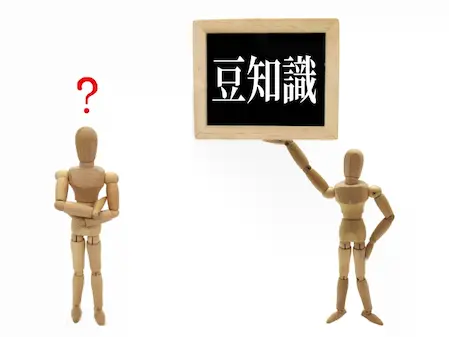企業や個人事業主が銀行などから融資を受ける際、「信用保証協会」の保証が必要になることがあります。このときに発生する費用が「信用保証料」です。
信用保証料は、融資を受ける側が信用保証協会に支払う保証の対価であり、融資をスムーズに進めるための重要なコスト要素です。中小企業や創業間もない事業者にとっては、金融機関の信用審査を通過するうえで欠かせない仕組みといえます。
信用保証料の基本的な仕組み
信用保証料とは、信用保証協会が金融機関に対して「万一、借入者が返済不能になった場合に代わりに返済する」ことを保証するために徴収される手数料です。
保証協会はリスクを負う立場にあるため、融資額や返済期間、借入者の信用力などに応じて保証料率を設定しています。
たとえば、保証料率が1%で1000万円を借りる場合、10万円が保証料として発生します。保証料は一括払いが一般的ですが、地域や制度によっては分割払いを認めるケースもあります。
信用保証料率の決まり方
信用保証料率は全国一律ではなく、各都道府県の信用保証協会が定めています。
通常、融資制度や借入者の経営状況、業種、保証の種類(普通保証・特別保証など)によって異なります。また、自治体や国の補助制度を活用することで、信用保証料の一部または全部が軽減される場合もあります。たとえば、経営安定化を目的とした「セーフティネット保証」や「危機関連保証」では、保証料が引き下げられる特例措置が設けられることがあります。
信用保証協会を利用するメリットと注意点
信用保証協会を利用する最大のメリットは、金融機関からの融資を受けやすくなる点です。
特に、創業期や財務基盤が脆弱な中小企業は、担保や保証人を用意するのが難しい場合があります。そのようなときに信用保証協会の保証を受けることで、金融機関は安心して融資を実行できるのです。
ただし、保証料というコストが発生すること、そして保証協会が代位弁済した場合は最終的に借入者に求償される(保証協会へ返済義務が生じる)点には注意が必要です。
士業(行政書士)の視点
信用保証料の計算や補助制度の適用は、制度内容や自治体の施策によって複雑に変わります。
行政書士や中小企業診断士などの専門家は、事業計画書の作成支援や保証制度の選定サポートを行うことができます。たとえば、信用保証協会とのやり取りを円滑に進めるための事業計画書の整備や、自治体補助金を併用した資金繰り設計などは、士業の専門的サポートが有効です。
信用保証料を軽減するための工夫
信用保証料は、事業者の信用力向上によって低減が期待できる場合もあります。
財務内容を改善し、税務申告や決算書類の透明性を高めることが、保証料率引き下げの要因となることがあります。
また、自治体や商工会議所などが行う「保証料の補助」制度を活用すれば、実質的な負担を抑えることも可能です。特に新型コロナウイルスや経済危機時には、緊急支援として保証料を全額免除する施策が実施されるケースもあり、最新情報を確認することが大切です。
まとめ:信用保証料を理解して賢く資金調達を行おう
信用保証料は、融資を受けるうえで避けて通れないコストですが、その役割を正しく理解すれば安心して資金調達を進めることができます。
特に中小企業や個人事業主にとっては、信用保証協会を通じた融資制度が経営安定の鍵を握ることも少なくありません。保証料の金額や補助制度は自治体や融資制度によって異なるため、申請前に行政書士や中小企業診断士などの専門家へ相談することで、最適な制度選択とコスト削減が実現します。
信用保証料を単なる「費用」としてではなく、「信用の橋渡し」として捉えることが、持続的な事業成長への第一歩といえるでしょう。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】