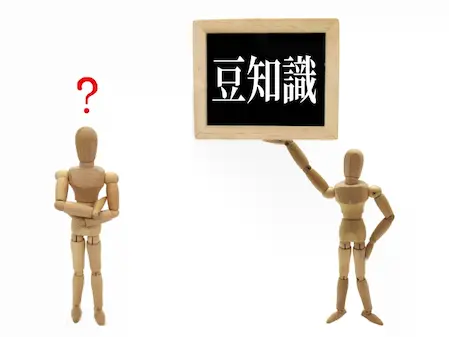かつては創業時に融資を受ける際、「連帯保証人」を求められることが一般的でした。
しかし現在では、制度融資や日本政策金融公庫の創業支援制度において、第三者の連帯保証人を原則不要とする方針が広く採用されています。
これは、創業者の挑戦を後押しし、過度な個人負担を避けるための制度的な改善です。本記事では、連帯保証人の基本的な意味と、創業融資における現在の扱い、注意すべきポイントについて専門家の視点から詳しく解説します。
連帯保証人の定義と法的責任
連帯保証人とは、債務者と同等の責任を負う保証人のことを指します。
通常の保証人は、まず債権者が債務者本人に請求するよう求める権利(催告の抗弁権)や、債務者の財産を優先して差し押さえるよう主張できる権利(検索の抗弁権)を持ちます。
しかし、連帯保証人にはそれらがなく、債権者は借主と同様に、連帯保証人に対して直接返済を請求することが可能です。そのため、法的責任が極めて重く、借主と同様に返済義務を負うことになります。
創業融資では連帯保証人が原則不要
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」では、第三者の連帯保証人を原則として不要としています。
これは、創業者の自己責任原則を重視し、事業計画の妥当性と将来の返済能力で審査を行うという考えに基づいています。金融機関や自治体の制度融資でも、信用保証協会が保証を行うことで、個人が保証人になる必要がない仕組みが整っています。したがって、家族や知人に保証人を頼む必要は基本的にありません。
例外的に求められるケース
もっとも、すべての融資で保証人が完全に不要というわけではありません。例えば、創業者本人が法人を設立して融資を受ける場合、代表者本人が「代表者保証」を求められることがあります。
民法改正と保証契約の保護制度
2020年の民法改正により、事業性融資における個人保証には「極度額(上限額)」の明記が義務化されました。これにより、保証人が無制限の債務を負うリスクが制限されています。
さらに、保証契約には書面または電子契約が実務上求められています。
まとめ
連帯保証人は本来、借主と同等の返済責任を負う非常に重い立場ですが、創業融資においては制度の改善により、原則として第三者の連帯保証人は不要となっています。
とはいえ、代表者保証や例外的な保証が求められる場合もあるため、契約内容を慎重に確認することが重要です。融資の準備段階から士業などの専門家に相談し、安心して創業資金を確保できるよう準備を進めましょう。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】