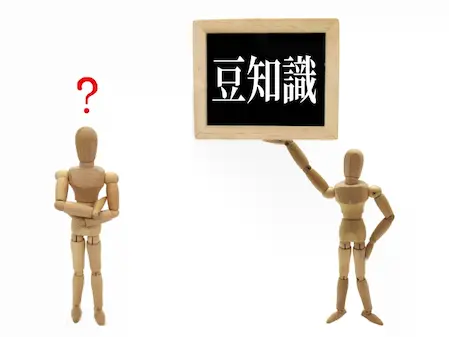起業やスタートアップの立ち上げ時には、資金調達が最初の大きな壁になります。
「自己資金だけでは不安」という声は多く、融資制度を探している創業者はとても多いのが実情です。この記事では、スタートアップ企業でも利用できる代表的な融資制度と、実務でのポイントをわかりやすくまとめて解説します。
結論:スタートアップでも利用できる公的融資はある
結論として、スタートアップや創業後まもない企業でも利用できる融資制度は複数存在します。
特に「日本政策金融公庫(公庫)の創業融資」や「自治体の制度融資」は、実績の乏しい創業期でも審査を受けやすい制度として広く利用されています。
主な制度としては、以下のようなものがあります。
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
- 自治体による「制度融資(信用保証協会付き)」
これらは実績がない企業でも申請可能で、創業資金、設備投資、運転資金に広く活用できます。
解説:公庫の創業融資は最も利用されやすい制度
スタートアップが初期に利用しやすいのは、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」です。無担保・無保証で利用できることが大きな特徴で、創業前から申請できる点も利便性が高いポイントです。
また、自治体の制度融資は、信用保証協会を通じた保証付き融資であり、民間金融機関からの借入を後押しする仕組みになっています。金利が低く、自治体が一部負担するケースもあるため、資金繰り改善に役立ちます。
さらに、自治体を通さず、民間金融機関と保証協会の2者で融資をすることもできます。
よくある誤解:スタートアップは融資が受けられない?
「スタートアップは実績がないから融資は難しい」という誤解は多いですが、公的融資については必ずしもそうではありません。創業計画、自己資金、開業業種の経験があれば、実績がなくても審査に通る可能性があります。
柏市で実際に創業融資を受けた成功事例はこちら
実務での注意点:事業計画書の完成度が審査を左右する
創業期の融資では「数字の根拠」と「実現可能性」が大きく評価されます。そのため、以下の点に注意して準備すると成功率が高まります。
- 売上見込みの根拠を明確にする(市場規模・顧客層・競合分析)
- 創業者の経験や実績を丁寧に説明する
- なぜ今このビジネスが必要かを論理的に示す
- 資金の使い道を明確にする(運転資金・開発費・設備費など)
- 事業計画の数字と説明内容の整合性を保つ
加えて、制度融資の場合は「金融機関面談」と「保証協会審査」の二段階があるため、準備不足があると時間がかかる傾向があります。
士業によるサポート内容:専門家に依頼すると通過率が上がりやすい
行政書士は、以下のような形で創業融資をサポートできます。
- 事業計画書の作成支援
- 売上・経費の数値検証と整合性チェック
- 公庫担当者との面談同席
- 制度選び(公庫・制度融資)
- 金額や返済条件などの提案
特に、初めて融資を受ける創業者は書類作成の経験が少ないため、専門家の支援があることで大きく成功率が高まります。
まとめ:スタートアップは早めの融資準備が成功のカギ
スタートアップは初期段階の資金繰りが事業継続の重要なポイントです。公庫や保証協会の融資制度は創業期でも利用しやすく、計画的な準備を行えば十分に活用できます。
どの制度が最適かはビジネスモデルや資金使途によって異なるため、迷った場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。適切な制度を選び、成長ステージに応じた資金調達を進めていきましょう。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】