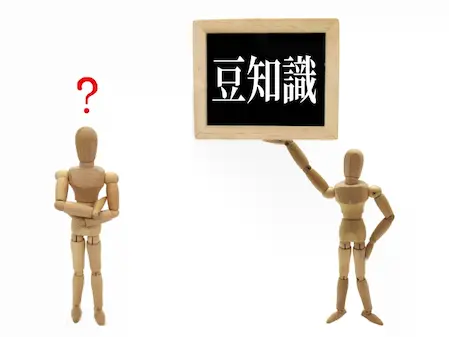これから開業する方にとって、「創業融資」は非常に重要な制度です。
しかし、融資を受ける際に「保証人が必要なのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
特に個人事業主や小規模な法人を立ち上げようとしている方にとって、保証人の有無は大きな心理的・実務的負担となります。
この記事では、創業融資における保証人の必要性について、制度の概要や注意点をわかりやすく解説します。
創業融資に保証人は原則不要
結論から言えば、多くの創業融資制度では「保証人は原則として不要」です。
特に、日本政策金融公庫(日本公庫)が実施している「新規開業・スタートアップ支援資金」では、第三者の保証人を立てる必要はありません。これは、創業期の起業家の資金調達を支援し、事業開始を後押しするために設計された制度だからです。
ただし、制度によっては「法人の場合は代表者が連帯保証人になる」ケースがあり、完全に無保証での融資とは限りません。詳細は制度の種類や融資額、信用状況によって異なるため、個別に確認することが大切です。
なぜ保証人不要の制度があるのか
創業直後の企業や個人事業主は、まだ実績や信用が十分にないことが一般的です。そのため、過去には「第三者保証人」を求めるケースも多くありましたが、それが資金調達の障壁となることも少なくありませんでした。
こうした背景から、日本政策金融公庫などの公的金融機関では、創業者のチャレンジを後押しする目的で、無担保・無保証人での融資制度が整備されました。具体的には、「新規開業・スタートアップ支援資金」などが該当します。
なお、無担保・無保証とはいえ、審査はしっかりと行われるため、事業計画や資金使途、返済見込みなどの書類準備は重要です。
よくある誤解
「保証人がいないと絶対に融資は通らない」と誤解している方がいますが、これは過去の融資制度のイメージが強く残っているためです。実際には、創業融資の多くが保証人不要となっており、しっかりとした準備と対策があれば、個人事業でも融資を受けられる可能性は十分にあります。
また、「保証人をつければ審査が有利になる」と考える方もいますが、日本政策金融公庫の創業融資においては、保証人の有無よりも事業計画や返済能力が重視されます。
実務での注意点
法人で創業する場合、代表者が「連帯保証人」となるケースがあります。これは、代表者自身の責任を明確にするためであり、第三者保証とは意味が異なります。
また、地方自治体の制度融資を利用する場合には、信用保証協会の保証を受けることになりますが、この場合でも原則として第三者保証人は不要です。ただし、事業の内容や信用状況により例外もあるため、事前に金融機関や保証協会に確認することが重要です。
専門家による支援
創業融資を受ける際は、行政書士や中小企業診断士などの専門家に相談することで、スムーズな書類作成や審査対応が可能になります。特に事業計画書の作成は、融資の審査結果に大きく影響するため、専門家のアドバイスを受けながら準備することをおすすめします。
また、保証人の要否について不安がある場合でも、専門家であれば制度の詳細を説明し、適切な対応策を提案してくれます。融資を成功させるためのパートナーとして活用すると良いでしょう。
まとめ
創業融資においては、第三者保証人は原則として不要な制度が多く、個人事業でも安心して申し込むことができます。ただし、法人の代表者が連帯保証人となるケースや、制度ごとの細かな条件には注意が必要です。安心して創業の第一歩を踏み出すためにも、専門家のサポートを受けながら、制度内容をしっかり理解して活用しましょう。
詳細はこちら|創業融資サポート専門【かきざき行政書士事務所】